就活でグループディスカッションを避けて通るのは難しく、やらなければならない時が必ずやってきます。とはいえ、結局声が大きくて自頭の良い人が有利になるような気がして苦手意識を持つ方も多くいるのではないでしょうか。そこで今回は、第一印象でおとなしそうと毎回言われる筆者が、メーカーのグループディスカッションを15回受けて全て合格するうえで意識したポイントをご紹介します。
Summary
大切な3つの考え方とメーカーのディスカッションで多いテーマ
「論理性」「主体性」「チームワーク」の姿勢
以下の記事に記載されているように、グループディスカッションではこの3つが重要であり、評価の対象となります。
参考記事はこちら:企業はここを見る!高評価がもらえるグループディスカッション
常にこの3項目を頭に浮かべながら発言をしましょう。
メーカーでよく見かけるお題
グループディスカッションのテーマは、一般的に「幸せとは?」といったような抽象的なお題や、2つの意見に分かれて討論を行うタイプなど多岐にわたりますが、メーカーでは「社員として考えるテーマ」がよく見られます。これは、「自社製品を使った新規提案」や「会社の人事としてどの学生を採用するか」などの学生全員が同じ企業の社員という設定で議論するタイプです。
社員として考えるテーマはチームワークを意識する
先ほどグループディスカッションには論理性、主体性、チームワークが重要とお伝えしましたが、このタイプのお題ではチームワークが重要になります。
初対面の人と議論をすると言っても、同じ企業の社員同士という設定なので、自分の意見の背景に企業の利益を考えた発言が求められます。
これを忘れがちになってしまうのが、「同じ社員としてディベートをするタイプ」です。どうしても対立側を論破して自分たちの意見を押し通したくなりますが、対立側もチームメイトと捉えながら議論を進めるチームワークが求められます。
おだやかタイプの学生のグループディスカッションでの意識と役割
とりあえず発言しようという意識を持つ
もちろん何も考えず、ただ思いついたことを口にするのは自分の評価を下げてしまうだけでなく、グループ全体の進行を止めてしまう原因になります。当然のことのように思えますが、議論の結論を固める段階で誰かが急に新しい提案をするなんてこともよくあります。
ここで伝えたいのは、議論のフェーズを踏まえたうえで臆せず発言するということです。
筆者もそうでしたが、おだやかなタイプの方は自分の意見が間違ってる気がして、あまり発言できなくなってしまうことがあります。ですが周りの話を聞いて考えた意見であれば、極端にズレた内容になることはほとんどありません。
筆者の場合、もし他の学生に意見が受け入れられなかったとしても、考えるべきことが洗練されたと前向きに考えるようにしていました。
自分に何ができるのかを知る
ディスカッションに必要な3つのポイントを理解した次は、自分が議論で活かせる強みを考えてみて下さい。
例えば、全体を俯瞰して違う視点からのアイデアを考えることや、話が脱線していないかを意識することなど、複数の強みを見つけておくのが良いでしょう。議論を行う前に自分に何ができるかを考えておくことで、本番で何をすればいいか分からないというような事態を防ぐことができます。
議論に必要な役割を考える
ディスカッションが始まれば、自然とそれぞれの学生の立ち位置が決まってきます。そうしたら次はディスカッションを進める中で何が足りないのか、求められているのかを考えます。その欠けている役割が見つかったのなら、自分の強みを活かしながらディスカッションを最善と呼べる結論に導きましょう。
筆者の場合、グループでアイデアを出すことに優れている学生が多ければ、自らも発言しながら議論を次の段階に持っていく役割を果たしたり、それとは逆に他の学生で意見をまとめて議論の方向性を作ることが得意な学生がいれば、方針の問題点や解決策を提案するようにしていました。
おだやか系筆者が実践したメーカーのグループディスカッション攻略
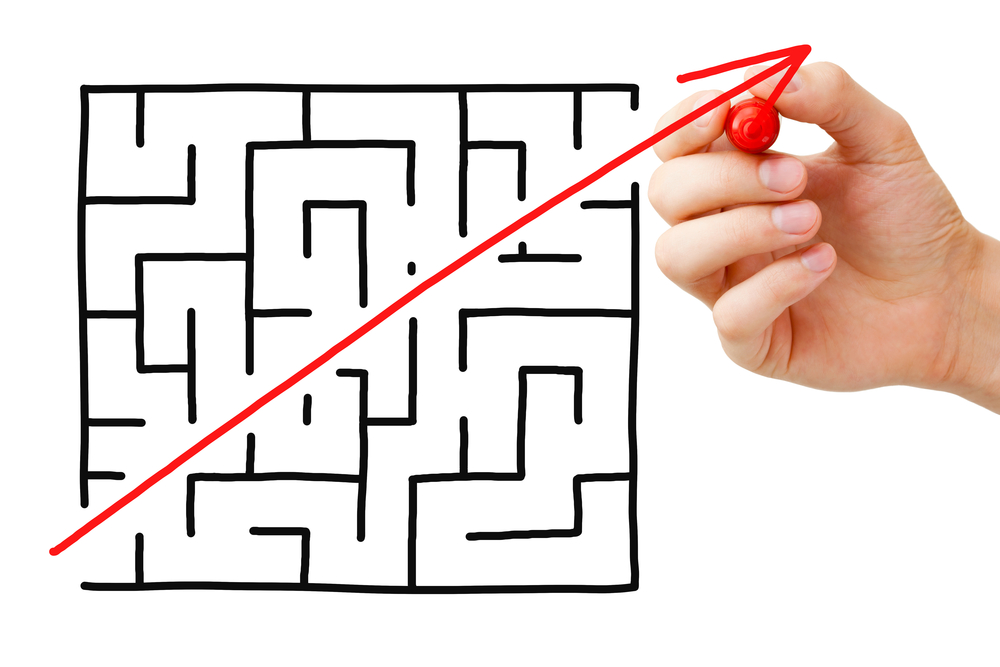
我が強くなくても、体育会系の雰囲気でなくてもグループディスカッションに貢献することは十分可能です。「論理性」「主体性」「チームワーク」を念頭に置きながら実践したテクニックについてご説明します。
開始時間までに周りと話しておく
選考が始まる前に他の学生と話してもあまり選考に影響が内容に思うかもしれません。しかし、この時間に会話しておくことで話しやすい雰囲気を作り、同じチームの学生の性格をある程度把握することができます。これはディスカッションを進行するためにも役立ちます。
とにかく人の話を聞いている姿勢を示す・メモをとる
始めは熱心に人の話を聞いていても、集中力が切れて後半はうわの空になってしまう学生は少なくありません。聴く姿勢は「主体性」と「チームワーク」という点でも非常に重要です。さらに他の学生の話を真剣に聞くことで、議論を進める中でカギとなるようなアイデアを思いつくかもしれません。
議論の最中は意見を聞いたり発言したりと忙しいため、すぐに忘れてしまいます。そのためにも、これは良いと思った意見はどんどんメモしておきましょう。
また、通常のグループディスカッションでは、議論の初めに学生全員が各々の意見を発言する時間があります。この時に良いと思った意見に加えて、気になる点があればその質問事項もメモしておくと役立ちます。
他の学生の意見を取り入れた新しいアイデアを考える
議論のメインとして採用されるアイデアは1つか2つとほとんどの意見は忘れ去られてしまいます。そこで始めに書いたメモを利用します。議論を進めるうちに、最初と方針が変わることがよくあります。そんなときに誰かの意見を改めて持ち出して、そこに自分の意見も加えます。
このとき、ただ他人の意見を繰り返すだけではあまり主体性が感じられないので、自分の意見も伝えることが大切です。
(例)目的が○○ということなので、Aさんの最初のアイデアを活用できると思います。さらに××(自分のアイデア)を考慮するのはどうでしょうか。
意見を採用された学生も悪い気はしないので、こちらの意見にほぼ必ず賛同してくれます。他の学生にとっても全く新しいアイデアではないので受け入れて貰いやすいです。
疑問形で発言する
ディスカッションの最中、「○○だと思います」と発言しても誰も反応してくれないなんてことが時々あります。筆者は初めてのグループディスカッションでこれを経験して心が折れそうでした。それからは意見を無視されることを防ぐために、疑問形で投げかけるということを意識するようにしています。質問されたら答えざるを得ないので、議論の活性化チームワークにもつながります。
議題や前提条件を再確認する
ディスカッションを引っ張っていくのではなく、後ろから支える方法です。意見を述べるだけでなく、情報の認識に誤解がないか確認することも非常に大切です。
途中で会話についていけなくなってしまったり、あるいは上手く議論が進んでいるように思えていたけど、実はどちらかが勘違いしていて最後の最後でまとまらなかったというような事態を防ぐことができます。さらにこの発言によって、自分だけでなく他のメンバーの手助けにもつながります。ですがこの発言を何度も繰り返すのは、主体性がないことと同じになってしまうので、ここぞというときにだけ使いましょう。
苦手意識を克服するには実践あるのみ
選考回数が少ない企業ほど、グループディスカッションは学生を大きくふるいにかけるポイントになるので十分な対策をしたいものです。しかし、いくらインターネットで知識を得てもアウトプットできなければ意味がありません。
志望企業のグループディスカッションに臨む前に、キャリアセンターやセミナーの対策講座などである程度経験を積んで、本番で実力を発揮できるようにしておきましょう。


