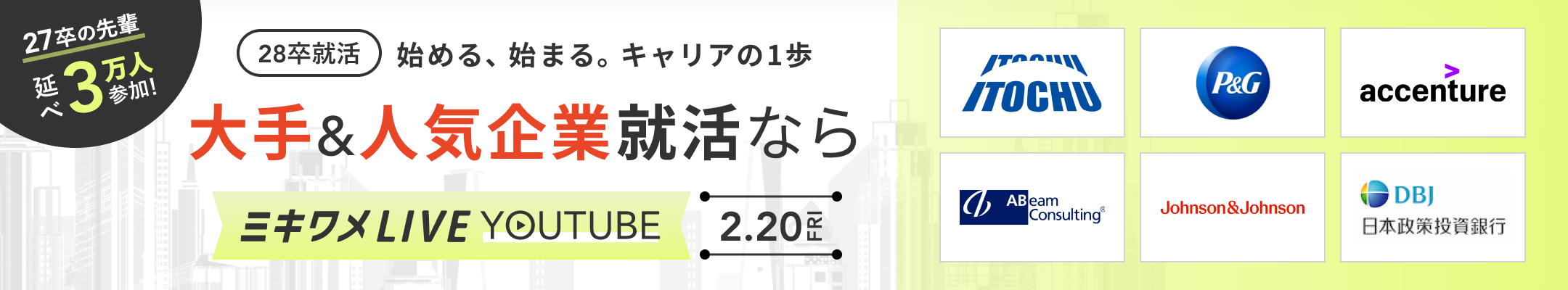こんにちは!ミキワメ運営局の大野です。
今回はメーカーの業界分析第二弾「フレームワークで分析してみた」です。
MBA(経営学修士)の授業で用いる、コスト構造分析の発想と5フォース分析を用いてメーカーを解剖していきますよ!!
Summary
はじめに
前回の記事では、製造業の基本情報と市場動向について深掘りしました。
今回は、製造業のコスト構造と競争環境にさらに踏み込んでいきます。
就活生の皆さんは、企業説明会や会社案内で製造業の表面的な情報には触れる機会が多いと思います。
しかし、その裏側にある「お金の流れ」や「競争のダイナミズム」については、なかなか知る機会がないのではないでしょうか。
この記事では、製造業のコスト構造分析とポーターの5フォース分析を通じて、業界の深層に迫ります。
これらの視点は、就職活動中の企業研究はもちろん、入社後のビジネス理解にも大いに役立つはずです。それでは、製造業の舞台裏に潜入していきましょう!

製造業のコスト構造を解剖する
まずは、製造業のコスト構造に切り込んでいきます。「モノづくり」と一言で言っても、その裏側には複雑な「お金の流れ」があります。
これを理解することで、企業の戦略や課題がより鮮明に見えてくるでしょう。
2.1 原材料費:製造業の「大食漢」
製造業最大のコスト項目が原材料費であることは、多くの方がご存知かもしれません。
しかし、その規模と影響力の大きさは、想像を超えるものがあります。
【衝撃の事実】
- ・製造業の売上高に占める原材料費の割合は、実に40〜60%にも達します。
- ・自動車産業では、1台の車の製造原価の約70%が部品代(つまり原材料費)です。
これは何を意味するのでしょうか?
例えば、200万円の車を販売したとして、そのうち140万円は部品メーカーに支払われているということです。
残りの60万円で人件費や設備費、利益を捻出しなければならないのです。
【就活生の皆さんへのヒント】
企業研究の際は、その会社の主要な原材料や調達方法に注目してみましょう。
例えば:
- ・主要サプライヤーは誰か?
- ・原材料の価格変動にどう対応しているか?
- ・独自の調達戦略はあるか?
これらの点を押さえることで、その企業の強みや課題が見えてくるはずです。

2.2 人件費:日本製造業の「アキレス腱」?
製造業における人件費は、通常売上高の15〜25%程度を占めます。
一見それほど大きくないように思えるかもしれません。
しかし、日本の製造業にとって、この人件費が大きな課題となっているのです。
【意外な事実】
- ・日本の製造業の人件費は、中国の約10倍、東南アジアの約5倍です。
- ・それにもかかわらず、日本企業の従業員1人当たりの売上高は、欧米企業の約半分にとどまっています。
つまり、「高コスト・低生産性」という難しい方程式に直面しているのです。
【最新トレンド】
この課題に対応するため、日本の製造業では次のような取り組みが活発化しています
例えば:
- ・RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による間接業務の自動化
- ・AI・IoTを活用したスマートファクトリー化
- ・「ジョブ型雇用」の導入による人材の最適配置
【就活生の皆さんへのアドバイス】
面接で「御社の人材戦略について教えてください」と質問してみましょう。
その回答から、その企業の課題意識や先進性が垣間見えるはずです。
2.3 設備投資:製造業の「命綱」
製造業は「装置産業」とも呼ばれます。
つまり、最新鋭の設備を持っているかどうかが、その企業の競争力を大きく左右するのです。
【驚きの数字】
- ・製造業の設備投資額は、2021年度で約14兆円。これは日本のGDPの約2.5%に相当します。
- ・半導体産業では、最新鋭の工場建設に1兆円以上かかることも珍しくありません。
【知られざる事実】
設備投資には「両刃の剣」的な側面があります。
最新設備は競争力の源泉となりますが、一方で巨額の減価償却費という重荷にもなるのです。
例:
最新鋭の半導体工場(1兆円)を10年で償却すると、毎年1,000億円のコストが発生します。需要が減少した場合、このコストが重荷となります。
【最新動向】
このリスクを回避するため、最近では次のような動きが見られます
例えば:
- ・競合他社との共同投資(例:ルネサスとTSMCの提携)
- ・レンタル工場の活用(例:アップルの製造パートナーであるフォックスコンの戦略)
- ・クラウドファンディングを活用した設備投資(中小企業で増加中)
【就活生の皆さんへの洞察】
企業研究の際は、その会社の設備投資戦略にも目を向けてみましょう。
積極投資している企業は成長志向が強い可能性が高く、逆に投資を抑制している企業は慎重な経営方針を取っている可能性があります。

2.4 研究開発費:未来への「種まき」
製造業にとって、研究開発は生命線です。
しかし、その重要性の割に、研究開発費の実態はあまり知られていません。
【意外な事実】
- ・日本の製造業の研究開発費は、売上高の平均3〜8%程度です。
- ・しかし、医薬品産業では20%以上、自動車産業でも5〜6%に達することがあります。
【隠れた課題】
研究開発費の多寡だけでなく、その「効率」も重要な指標です。
例:
日本の自動車メーカーの研究開発費は世界トップクラスですが、特許の「質」(他社からの引用数など)では欧米メーカーに後れを取っているという分析もあります。
【最新トレンド】
研究開発の効率化のため、次のような取り組みが増えています
例えば:
- ・オープンイノベーション(例:トヨタのTRI-ADによる自動運転技術の開発)
- ・CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の設立(例:パナソニックのSpinning Top)
- ・大学との産学連携(例:日立製作所の「日立京大ラボ」)
【就活生の皆さんへのヒント】
面接で「御社の研究開発の特徴は何ですか?」と質問してみましょう。
その回答から、その企業の技術戦略や将来ビジョンが見えてくるはずです。
ポーターの5フォース分析で読み解く
製造業の競争環境
次に、マイケル・ポーターが提唱した5フォース分析を用いて、製造業の競争環境を詳細に見ていきましょう。
この分析は、業界の構造を理解し、その中での自社の位置づけを把握するのに非常に有効です。
3.1 新規参入の脅威:意外な「穴」が存在する
一般的に、製造業は設備投資や技術力の壁が高く、新規参入が難しいと考えられています。
しかし、実際にはもっと複雑な状況があります。
【意外な事実】
- ・自動車産業:テスラの台頭により、100年以上続いた業界構造が大きく変わりつつあります。
- ・家電産業:中国のXiaomiやOPPOなど、新興勢力が急速にシェアを拡大しています。
【最新トレンド】
新規参入を容易にする要因が増えています
例えば:
- ・デジタル技術の発展:3Dプリンティング技術により、試作品製作のコストが大幅に低下
- ・モジュール化の進展:スマートフォンなど、部品の組み立てだけで製品化が可能に
- ・クラウドファンディング:資金調達の敷居が低下
【就活生の皆さんへの洞察】
志望企業が属する業界で、最近急成長している新興企業はないか調べてみましょう。
その企業の戦略から、業界の「穴」や変化の兆しが見えてくるかもしれません。
3.2 代替品の脅威:「破壊的イノベーション」の温床
製造業において、代替品の脅威は常に存在します。しかし近年、その脅威が加速度的に高まっています。
【衝撃の事例】
- ・カメラ産業:スマートフォンの普及により、コンパクトデジタルカメラ市場が激減
- ・腕時計産業:Apple Watchの登場で、従来の腕時計メーカーが苦戦
- ・照明産業:LED技術の台頭により、白熱電球や蛍光灯メーカーが淘汰
【最新動向】
代替品の脅威は、単なる「製品」の置き換えにとどまりません
例えば:
- ・所有からシェアへ:カーシェアリングの普及による自動車販売への影響
- ・物質からデジタルへ:電子書籍の台頭による紙の書籍市場の縮小
- ・リアルから仮想へ:VR技術の発展によるフィットネス機器市場への影響
【就活生の皆さんへのアドバイス】
志望企業の製品やサービスが、将来的に何に代替される可能性があるか考えてみましょう。
その洞察を面接で披露できれば、鋭い視点を持っていると評価されるかもしれません。
3.3 買い手の交渉力:B2BとB2Cの「意外な違い」
製造業における買い手の交渉力は、B2B(企業間取引)とB2C(消費者向け取引)で大きく異なります。
【B2Bの実態】
- ・自動車部品産業:完成車メーカーの要求する「毎年の原価低減」が常態化
- ・電子部品産業:スマートフォンメーカーの発注量変動が、部品メーカーの経営を直撃
【B2Cの最新トレンド】
- ・SNSの影響力増大:消費者の声がダイレクトに企業に届くようになった
- ・カスタマイズ要求の高まり:「パーソナライズ」が当たり前の時代に
【知られざる事実】
プラットフォーマーの台頭により、B2BとB2Cの境界が曖昧になりつつあります。
例:
Amazonのマーケットプレイスでは、メーカーが直接消費者に販売可能に。
【就活生の皆さんへのヒント】
志望企業のビジネスモデルが、B2BとB2Cのどちらに近いかを考えてみましょう。
そして、その特性に応じた戦略を持っているかどうかをチェックしてみてください。
3.4 売り手の交渉力:「隠れた主役」たち
製造業において、原材料や部品の供給者(売り手)の存在感が増しています。
【意外な事実】
- ・自動車産業:電気自動車の普及により、バッテリーメーカーの発言力が急上昇
- ・スマートフォン産業:画面用有機ELパネルの供給者が限られ、製品開発に大きな影響
【最新動向】
- ・サプライチェーンのボトルネック化:半導体不足が様々な産業に影響
- ・環境規制の影響:「グリーン調達」の要求が高まり、対応できる売り手が限定的に
【隠れた課題】
原材料の調達リスクが高まっています
例えば:
- ・レアアース:中国依存のリスク
- ・コバルト:児童労働問題への対応
- ・パーム油:熱帯雨林破壊への懸念
【就活生の皆さんへの洞察】
志望企業の主要な原材料や部品は何か、そしてそれらの調達先にどのような特徴があるか調べてみましょう。
その企業の強みや課題が見えてくるはずです。

3.5 既存競争の激しさ:「破壊と創造」のるつぼ
製造業における既存企業間の競争は、グローバル化やデジタル化の影響でますます激化しています。
【衝撃の事実】
- ・テレビ産業:かつて世界市場を席巻した日本メーカーのシェアが急落。韓国・中国メーカーが台頭。
- ・スマートフォン産業:2007年のiPhone登場以降、Nokia、BlackBerryなど老舗メーカーが市場から撤退。
【最新トレンド】
競争の軸が変化しています:
- ・ハードウェアからソフトウェアへ:例えば自動車産業では、自動運転技術や車載OSの開発が競争力の源泉に。
- ・プロダクトアウトからマーケットインへ:顧客ニーズを起点とした製品開発が主流に。
- ・所有から利用へ:製品販売だけでなく、サブスクリプションモデルの導入が加速。
【知られざる競争の実態】
- ・標準化競争:例えば、次世代通信規格「6G」の主導権を巡り、各国・各社が熾烈な競争を展開。
- ・人材獲得競争:AI・IoT人材の不足により、業界の垣根を越えた人材の引き抜きが活発化。
- ・特許競争:重要技術の特許を押さえるため、大規模な特許取得や他社特許の買収が進行。
【就活生の皆さんへのアドバイス】
志望企業の主要な競合他社を3社程度ピックアップし、それぞれの強みと弱みを分析してみましょう。
その上で、志望企業がどのような差別化戦略を取っているかを考察してみてください。この視点は面接でも役立つはずです。

まとめ:製造業の「現在地」と「未来図」
ここまで、製造業のコスト構造と競争環境について詳しく見てきました。これらの分析から浮かび上がる製造業の「現在地」と「未来図」をまとめてみましょう。
4.1 製造業の「現在地」
- ・コスト構造の変革期:原材料費や人件費の高騰に直面し、大規模な構造改革が進行中。
- ・デジタルシフトの加速:IoT、AI、ビッグデータなどのデジタル技術の導入が、競争力の鍵に。
- ・グローバル競争の激化:新興国企業の台頭により、従来の競争構造が大きく変化。
- ・サステナビリティの重要性増大:環境対応や社会的責任が、ビジネス上も重要な要素に。
4.2 製造業の「未来図」
- ・モノからコトへ:製品販売だけでなく、サービスやソリューションの提供が主流に。
- ・オープンイノベーションの普及:自前主義からの脱却が進み、外部との協業が一般化。
- ・サプライチェーンの再構築:地政学リスクや環境負荷を考慮した、新たな調達・生産体制の構築。
- ・循環型経済への移行:リサイクル、リユース、リデュースを前提とした製品設計・生産が標準に。
【就活生の皆さんへのメッセージ】
製造業は今、大きな変革期を迎えています。
これは、皆さんにとって大きなチャンスでもあります。
なぜなら、従来の常識や慣習にとらわれない、新しい発想や行動力が求められているからです。
企業研究や面接準備の際は、その企業が直面している課題や、将来に向けた取り組みにも注目してみてください。
そして、自分ならどのような貢献ができるか、具体的に考えてみましょう。それが、あなたの「強み」になるはずです。
製造業は、私たちの生活を支え、社会に大きな影響を与える重要な産業です。
その舞台裏を知ることで、皆さんの就活はより深みのあるものになるでしょう。この記事が、皆さんの製造業研究の一助となれば幸いです。
次回は製造業に属する企業の組織構造を解剖していきます!どんな仕事があるのか、一緒に見ていきましょう!