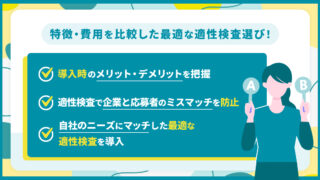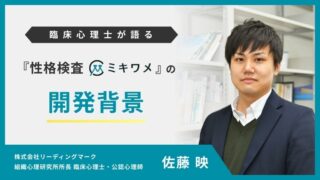昨今注目が集まっている「ウェルビーイング(well-being)」について、ご存知でしょうか。
「ウェルビーイング」は直訳すると「健康」や「幸福」を意味する言葉ですが、正確な意味や定義については認知されていないのが事実です。
この記事では、ウェルビーイングの意味や企業が取り組むメリット、実現させるためのポイントについて解説します。
ウェルビーイングに取り組んでいる企業の事例も紹介しているので、ぜひこの記事を参考に、自社に合った施策を考えてみてください。
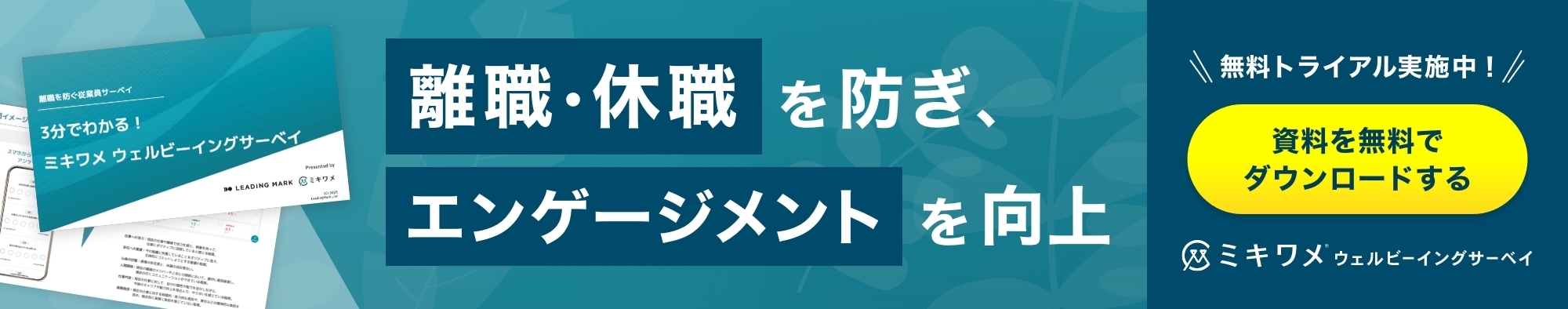
ウェルビーイングとは?意味や類語を解説

ウェルビーイング(well-being)とは、「肉体的・精神的・社会的に満たされた良好な状態」を意味します。直訳すると「健康」や「幸福」ですが、国や機関によって定義や意味はさまざまです。
たとえば、世界保健機関(WHO)憲章前文の一節では、ウェルビーイングを次のように定義しています。
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。
引用:日本WHO協会|世界保健機関(WHO)憲章とは(世界保健機関憲章前文(日本WHO協会仮訳)
厚生労働省では、次のように定義しています。
「ウェル・ビーイング」とは個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念
引用:厚生労働省|雇用政策研究会報告書 概要(案)(p.1)
どちらも、「病気にならない」「ケガをしない」という狭義の健康を意味する言葉ではないことが共通しています。したがって、ウェルビーイングは、「幸せを実感し、仕事や人間関係が良好な状態である」という広義の健康を指している言葉だといえるでしょう。
また、ウェルビーイングには、次のような近しい意味の言葉もあります。
| ウェルビーイングの類語 | 意味 |
| ウェルネス(welness) | より良く生きようとする生活態度 |
| ウェルフェア(welfare) | 福利厚生や福祉 |
| クオリティオブライフ(QOL) | 生活や人生の質 |
それぞれ意味は異なりますが、ウェルビーイングの要素や達成手段として捉えられる言葉です。
世界幸福度ランキングからみるウェルビーイングの現状
2023年の国別幸福度ランキングにおける日本の順位は、137カ国中47位です。幸福度ランキングは、次の6項目を加味して決定されます。
- 一人当たりのGDP
- 社会的支援
- 健康寿命
- 人生選択の自由度
- 他者への寛容度
- 国への信頼度
2022年の順位は146カ国中54位で、7位順位がアップしており、幸福度は上がっているといえます。しかし、GDP1位であるアメリカが1位、3位であるドイツが16位であるのに対し、GDP4位の日本は47位と主要7カ国のなかで最も低い順位なので、良い結果ではありません。
日本のウェルビーイングの現状は改善傾向にあるとはいえ、主要7カ国のなかではまだまだ改善点が多いといえるでしょう。
ウェルビーイングがビジネスで注目されている4つの要因

ウェルビーイングがビジネスで注目されている背景には、次の4つの要因があります。
それぞれの要因を理解したうえで、ウェルビーイングへの取り組みを検討しましょう。
ウェルビーイングがビジネスで注目されている理由について詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。
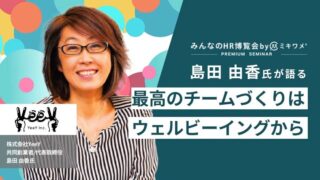
1.SDGsの推進
SDGs(エスディージーズ)は、「持続可能な開発目標」を意味します。2001年に策定されたミレニアム開発目標の後継にあたるもので、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標です。
SDGsでは、目標(ゴール)として17の項目を挙げています。そのうちの3つ目には「GOOD HEALTH AND WELL-BEING(すべての人に健康と福祉を)」が掲げられており、社会全体でウェルビーイングが求められていると理解できるでしょう。
2.ダイバーシティ経営の推進
ダイバーシティの直訳は「多様性」で、一般的には「性別や人種、価値観などにとらわれず、多様な人材が集まった状態」を意味しています。
現代のビジネスシーンでは、多様な価値観やバックグラウンドを持つ人とコミュニケーションをとる機会が増えてきました。同時に、働き方やライフスタイルも多様化し、次のような取り組みも進んでいます。
- 外国人労働者の受け入れ
- テレワークの浸透
- フレックスタイム制の導入
企業が従業員の多様性を尊重し、能力を最大限発揮できる環境を整備すること(ダイバーシティ経営の推進)は、従業員の幸福度や生産性の向上に欠かせません。そのため、ダイバーシティはウェルビーイングの実現の重要な要素として注目されています。
3.ワークライフバランスの見直し
仕事と生活を両立させるワークライフバランスは、働き方改革を推進させるための企業の重要な経営課題のひとつです。
ワークライフバランスの実現には、さまざまなメリットがあります。具体的な例は次のとおりです。
- 業務の拘束時間が減り、自分や家族の時間が増える
- 心のゆとりが生まれる
- やりがいやチャレンジ精神が生まれる
- メンタルが健全化する
ワークライフバランスに対する取り組みを見直すことで、仕事だけではなく、生活の充実や幸福(ウェルビーイング)を推進する企業が増えています。
4.労働人口不足と人材確保
日本では少子高齢化が進み、令和5年1月1日時点での日本の総人口は前年より80万人以上減少しています。
65歳以上の老年人口が増加傾向にあるのに対し、15歳以上65歳未満の生産年齢人口は減少傾向にあるため、今後も深刻な労働人口不足が予測されるのが事実です。
また、近年では終身雇用の崩壊や転職の一般化が進んだことからも、優秀な人材の確保が欠かせません。
企業は、これまで給与や待遇改善で人材の定着を図ってきました。しかし、人材の流動化が激しい昨今では、優秀な人材の確保には、従業員や家族の幸福を追求する姿勢が求められます。
人材獲得競争が激化しているからこそ、従業員の帰属意識やロイヤリティを向上させ、人材を定着させる必要があるでしょう。そのため、人材の確保には、ウェルビーイングを重視した労働環境を作ることが重要です。
ウェルビーイングを測定する2種類の指標

ウェルビーイングには、次の2種類の指標があります。
- ポジティブ心理学「PERMAの法則」
- ギャラップ社の5つの要素
ウェルビーイングに対する理解を深めるためには、それぞれが提唱する5つの要素を把握するのが重要です。
ウェルビーイングの指標について詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。

1.ポジティブ心理学「PERMAの法則」

ポジティブ心理学「PERMAの法則」は、ポジティブ心理学の第一人者であるセリグマン博士が提唱した理論です。次の5つの要素で構成された「持続的な幸福」を重要視しています。
- P:Positeve Emotion(ポジティブな感情)
- E:engagement(作業への没頭)
- R:Relationship(良好な人間関係)
- M:Meaning and Purpose(人生の意味や目的)
- A:Achievement/ Accomplish(目標達成)
各要素が向上することで、幸福度や充実度が高まり、ウェルビーイングな状態になるとされています。
P:Positive Emotion(ポジティブな感情)
Positive Emotionとは、愛や喜び・感謝・安らぎなどのポジティブな感情を表しています。
ネガティブな思考を打ち消すことで、感受性や創造性を高められるのが特徴です。思考や行動をプラスの方向に導けるため、未来の選択肢を広げられます。
E:Engagement(作業への没頭)
Engagementとは、夢中になって仕事を進めたり時間を忘れるほど作業に没頭したりして、物事に積極的に関わっている状態です。目の前のことに集中するため、作業効率が向上します。
また、何かに夢中になっている時は、ネガティブな感情を抱きにくく、ポジティブな感情を維持できるのが特徴です。
R:Relationship(良好な人間関係)
Relationshipとは、会社の同僚や上司・後輩・家族などと深い関わりを持って、信頼関係が構築できている状態です。他者から必要とされたり愛情を感じたりすることで、人生の幸福度を高められます。
一方で、積極的に関わりを持つだけでなく、他者との違いを認めたり不必要に比較したりしないことも重要です。自分にとって良好だと感じられる関係性も持つことによって、幸福を感じやすくなるでしょう。
M:Meaning and Purpose(人生の意味や目的)
Meaning and Purposeは、人生で重要することや価値を感じることなどを明確にしている状態です。一時的な楽しいや嬉しいといった感情ではなく、長期的な視点での価値観や優先順位を定めることで、人生の幸福度が高められます。
周囲がどう思うかよりも、自分が大切にしたい価値観や人生の意義を見つけることによって、幸せを感じられるでしょう。他者から見たら無意味であるような事柄でも、自分にとっては大切な価値観である場合も少なくありません。
A:Achievement/ Accomplish(目標達成)
Achievement/ Accomplishは、目標達成によって、自己肯定感が高められている状態を意味します。
自己肯定感とは、自分を受け入れることです。自分の考えや能力を認められれば、物事を進める原動力になります。
また、自分に自信が持てるようになるため、仕事にも前向きになり、業務パフォーマンスの向上が期待できるでしょう。ビジネスにおいては、資格や検定、昇進試験などへの挑戦も効果的です。
2.ギャラップ社の5つの要素
ギャラップ社の5つの要素とは、世界最大規模の世論調査会社であるギャラップ社が挙げている次の5つの構成要素です。
- Career Wellbeing(仕事とプライベートの両立)
- Social Wellbeing(良好な人間関係)
- Financial Wellbeing(良好な経済状態)
- Physical Wellbeing(良好な健康状態)
- Community Wellbeing(良好なコミュニティ形成)
ギャラップ社は160以上の国や地域でウェルビーイングに関する調査をしており、調査データは国連の「世界幸福度ランキング」にも利用されています。そのため、ギャラップ社の世論調査は、ウェルビーイングを語るうえで重要なポイントといえるでしょう。
①Career Wellbeing(仕事とプライベートの両立)
Career Wellbeingとは、仕事に熱意を持って取り組むだけでなく、プライベートの充実も考えられている状態です。
仕事とプライベートの両方を充実させることで、ウェルビーイングを目指せます。ワークライフバランスを考えるうえでも欠かせません。
仕事と家事、育児などの総合的な人生の幸福を構築するのが重要です。
②Social Wellbeing(良好な人間関係)
Social Wellbeingとは、上司や同僚・友人・家族などと良好な人間関係を築けている状態です。
良好な人間関係が築けていることによって、その幸せが周囲に伝わりやすい傾向にあります。ただし、交友関係の広さだけでなく、信頼や愛情を感じられる関係であることが重要です。
③Financial Wellbeing(良好な経済状態)
Financial Wellbeingとは、仕事に対して十分な報酬を得られており、適切な資産管理ができている状態です。
お金があることによって、幸福を感じやすくなります。一方で、経済的な不安があると心に余裕がなくなり、仕事や対人関係に悪い影響が出てしまうでしょう。
安定した生活を送るためには資産管理が欠かせません。
④Physical Wellbeing(良好な健康状態)
Physical Wellbeingとは、自分がやりたいことに取り組めるだけの健康状態やエネルギーを保てている状態です。
週2回以上の運動習慣がある人は、ストレスが少ない傾向にあるため、運動していない人よりも幸せに生活していると考えられています。また、身体だけでなく、ポジティブな思考を維持できるだけの心の健康も重要です。
心身の健康を保つことによって、仕事に対するモチベーションも上がりやすいでしょう。
⑤Community Wellbeing(良好なコミュニティ形成)
Community Wellbeingとは、所蔵している組織や地域との関係性が良好な状態であることを意味します。
家族や会社・地域など、生活するうえでは、さまざまなコミュニティに所属しなければなりません。そのため、コミュニティへの関わりが親密であれば、ウェルビーイングにつながりやすいとされています。
地域活動への参加や組織への寄付などを通して幸福度を向上させられるでしょう。
企業がウェルビーイングに取り組む4つのメリット

企業がウェルビーイングに取り組むことによって、次の4つのメリットを得られます。
メリットを理解することで、効果的にウェルビーイングに取り組めるでしょう。
ウェルビーイングのメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。

1.健康経営の増進
健康経営とは、従業員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に実践することです。
ウェルビーイングな経営をすることによって、従業員の幸福度が上がれば、幸福ではない場合と比較して欠勤率が41%低くなり、業務事故も70%減少するという研究成果も出ています。
健康経営が増進されれば、結果として企業や組織全体の活力向上に貢献できるでしょう。
2.生産性と創造性の向上
ウェルビーイングを意識した環境で働くことによって、やりがいや意欲を持って仕事に取り組めるようになるため、生産性が31%向上し、創造性は3倍になります。
心身が安定した環境下では、従業員の能力が十分に発揮されるようになるため、組織全体の生産性や創造性の向上も期待できるでしょう。
3.離職者の減少と人材の確保
ウェルビーイングが定着した職場では、従業員が精神的・肉体的に健康な状態で長く働けるため、離職率が50%低下します。
また、「ウェルビーイングに積極的に取り組む企業」というポジティブなイメージが広がることで、企業のブランド力が向上し、優秀な人材の確保や定着にもつながるでしょう。
4.従業員の満足度と業績アップ
ウェルビーイングを推進させることによって、従業員の労働環境に対する満足度が向上し、企業の売上が37%アップするという研究結果が出ています。
これは、従業員の満足度の向上により、仕事の生産性が高くなったことが要因です。
一方で、気持ちの落ち込みを放置した場合、生産性が35%低下すると指摘する研究結果もあります。精神的な問題によって、生産性を低下させないためにも、ウェルビーイングの取り組みが欠かせません。
ウェルビーイングを実現させるために人事ができる3つの施策

人事がウェルビーイングを実現させるためには、次に3つの施策が効果的です。
効果的な施策を実施することで、従業員の幸福度が上がり、企業の生産性向上が期待できるでしょう。
1.労働環境の見直し
従業員が心身に負担を感じる職場では、休職や離職につながってしまうため、労働環境の改善が欠かせません。次のような取り組みをすることで、従業員のストレスを減らせるでしょう。
- 長時間労働の改善
- 休日出勤・残業時間の削減
- テレワークの導入
- 定時退社の推奨
- 有給休暇取得の促し
1日の労働時間が10時間半を超えると、生活満足度は急激に低下するとされているので、長時間労働や休日出勤の削減は欠かせません。また、以下のようなデータもあります。
- 女性は労働時間が6〜7時間以上になると生活満足度が平均以下になる
- 男性は8時間を超えると徐々に満足度が下がっていく
- 所得の影響を取り除いた非金銭効果では、6時間を超えると生活満足度が平均以下になる
従業員の満足度を向上させるためには、むやみな残業は控え、労働環境の改善が重要です。
2.福利厚生の充実
福利厚生が充実している企業が、ワークライフバランスを整えやすい傾向にあります。ワークライフバランスの向上は、ウェルビーイングの実現にも効果的です。
福利厚生に次のような制度を導入することで、ワークライフバランスを向上させやすいでしょう。
- 育児・介護のサポート
- 住宅補助
- 食事手当
- インセンティブ制度の導入
- レジャー施設やフィットネスクラブの割引
特に、リフレッシュ休暇のような休暇に関する制度は、ウェルビーイングにつながりやすいとされています。
ウェルビーイングの向上について詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。

3.コミュニケーションの改善
円滑なコミュニケーションは、人間関係や仕事に関する悩みの解消に欠かせません。適切なタイミングでコミュニケーションの場を設けられれば、休職・離職の防止や生産性の向上にも効果的です。
株式会社リーディングマークが提供している『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』なら、従業員の性格や心理状態を元に、サポートが必要な社員を可視化できます。
AIが個々の社員に合ったマネジメントやケアの方法を提案してくれるので、離職率低下にもつながるでしょう。
ウェルビーイングに取り組む企業事例6選

ウェルビーイングに取り組む企業事例を紹介します。
| 企業名 | 取り組み |
| 味の素株式会社 | 従業員のセルフケアの促進 |
| ユニリーバ・ジャパン株式会社 | ワーケーション制度の導入 |
| 株式会社アシックス | 運動に重点を置いた取り組みの実施 |
| PwC Japanグループ | 多様な施策を展開 |
| Google合同会社 | 心理的安全性に着目 |
| イケア・ジャパン株式会社 | 全世界の従業員に一時金を支給 |
各企業の事例を参考に、自社に合ったウェルビーイングの施策を考えましょう。
ウェルビーイングの事例について詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。

1.味の素株式会社:従業員のセルフケアを促進
食品メーカーである味の素は、『味の素グループ健康宣言』を掲げ、従業員が心身の健康維持・増進ができる職場環境づくりに注力しています。
味の素の特徴は、従業員のセルフケアの促進です。たとえば、次のような取り組みを実施しています。
- 全員面談:従業員一人ひとりに合った健康支援
- カロママプラス:AIによる栄養管理アプリの提供
- MyHealth:可視化された健康情報を閲覧・活用できるポータルサイト
上記の取り組みが高く評価され、味の素は「健康経営銘柄2021」や「健康経営優良法人2021(ホワイト500)」に認定されています。
2.ユニリーバ・ジャパン株式会社:ワーケーション制度を導入
一般消費財メーカーであるユニリーバでは、自分も含めたすべての人が「幸せに働く」ことを目指し、ウェルビーイングを推進しています。
たとえば、ワーケーション制度である「WAA(ワー)」が有名です。「WAA」は、働く場所と時間の制限をなくす目的で設けられた制度で、多くの従業員が生産性の向上や生活改善を実感しています。
3.株式会社アシックス:運動に重点を置いた取り組みの実施
スポーツメーカーのアシックスは、『ASICS健康経営宣言』を策定し、従業員とその家族の健康的な生活の実現を目指して健康経営に取り組んでいるのが特徴です。
具体的には以下のような取り組みをしてます。
- 本社にあるスペースで終業後にスポーツを楽しめる
- 全社員に対してメンタルヘルス研修の実施
運動に重点を置いた取り組み方、ウェルビーイングの実現を目指しています。
4.PwC Japanグループ:多様な施策を展開
世界4大会計事務所のひとつであるPwCのJapanグループでは、「Be well, work well」を合言葉に、従業員が心身ともに健康で、高いモチベーションを保ちながら仕事に取り組める環境づくりを目指しています。
PwCでは、ウェルビーイングを次の4領域に分けているのが特徴です。
- Physical(身体)
- Mental(精神)
- Emotional(感情)
- Spiritual(生き方・働き方)
従業員や家族が、それぞれの領域で仕事やプライベートを充実させられるような多様な施策を展開しています。主な取り組みとしては次のとおりです。
- 法定検診以外の補助
- 予防接種の補助
- 年1回のストレスチェック
- 相談窓口の設置(産業医や看護師が常駐)
- 職場復帰支援プログラムの提供
これらの取り組みは、メンタル疾患の予防や早期発見、休職からの職場復帰にも効果が期待できます。
5.Google合同会社:心理的安全性に着目
Googleでは、2012年からチームで成果を上げる際に欠かせないものを見出すための調査を実施し、心理的安全性が圧倒的に重要だと結論付けられました。
心理的安全性とは、リスクのある行動を取ったとしても不安を感じない状態です。質問やミスに対して、メンバーが自分を責めたりバカにしたりしないと信じられることで、チーム内のコミュニケーションが活性化していくでしょう。
心理的安全性を高めるために、チーム内の面談や積極的なコミュニケーションを実施しています。
6.イケア・ジャパン株式会社:全世界の従業員に一時金を支給
IKEAでは、「Be yourself(自分らしくいること)」を大切にしています。「ビジネスの中心は人々」という考えを掲げており、従業員のことを「コワーカー(仲間)」と表現しているのも特徴です。
ウェルビーイングに関する以下のような取り組みをしていることで世界的に注目を集めています。
- メンタルヘルスに関するウェビナーの実施
- 有給休暇の取得推進
- e-ラーニングの提供
そのほかにも、2022年にはコロナ禍の経営を支えたとして、全世界のコワーカーに一時金を支給しています。
ウェルビーイングを推進して生きいきと働ける職場づくりをしましょう

ウェルビーイングを意識した取り組みをすることで、従業員の幸福度や充実度が高まるだけでなく、業務パフォーマンスや満足度が向上します。結果として、企業の成長や利益も期待できるでしょう。
また、ウェルビーイングを定着させるには労働環境の見直しや福利厚生の充実、コミュニケーションの改善が欠かせません。適切な環境が整えられれば、従業員の休職や離職率の低下にもつながります。
変化の激しい現代のビジネスシーンにおいて、優秀な人材を確保するためにも、欠かせない概念です。ウェルビーイングを推進し、社員一人ひとりが生きいきと働ける職場づくりを試みていきましょう。
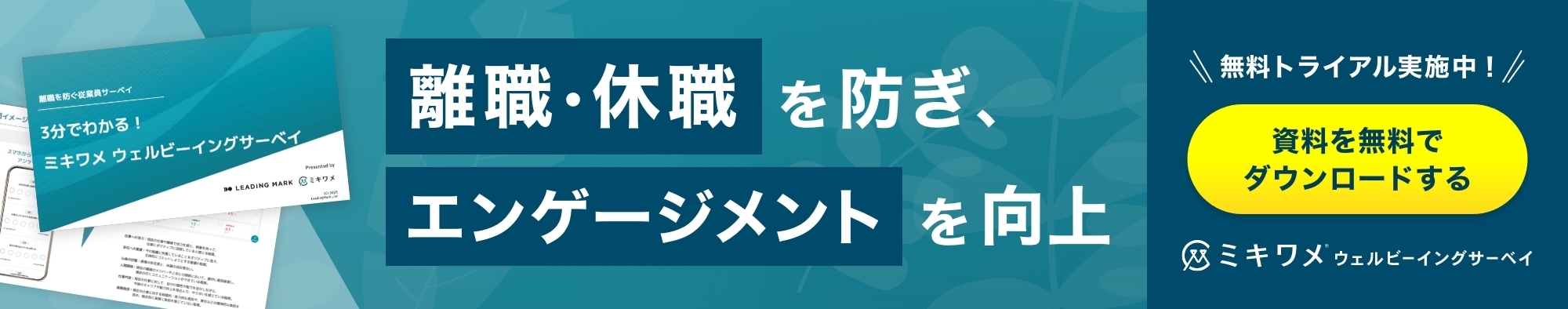
従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐパルスサーベイ。30日間無料トライアルの詳細は下記から。






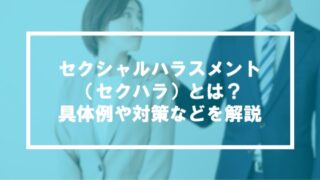

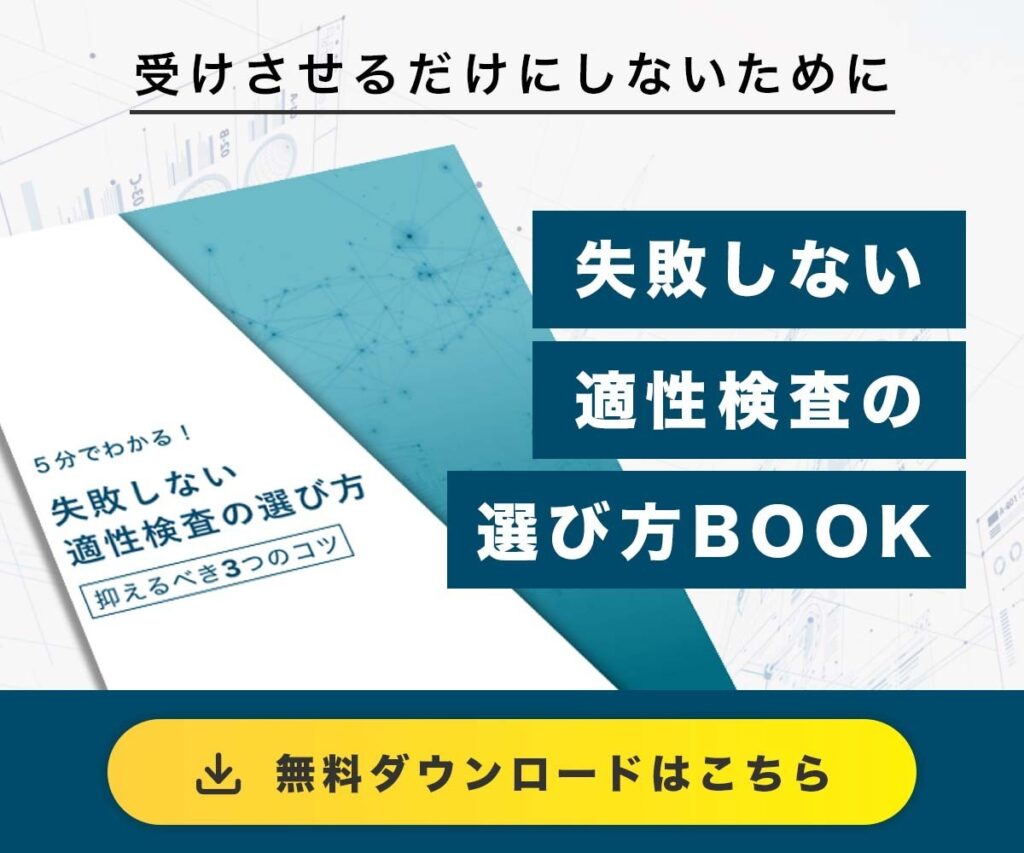
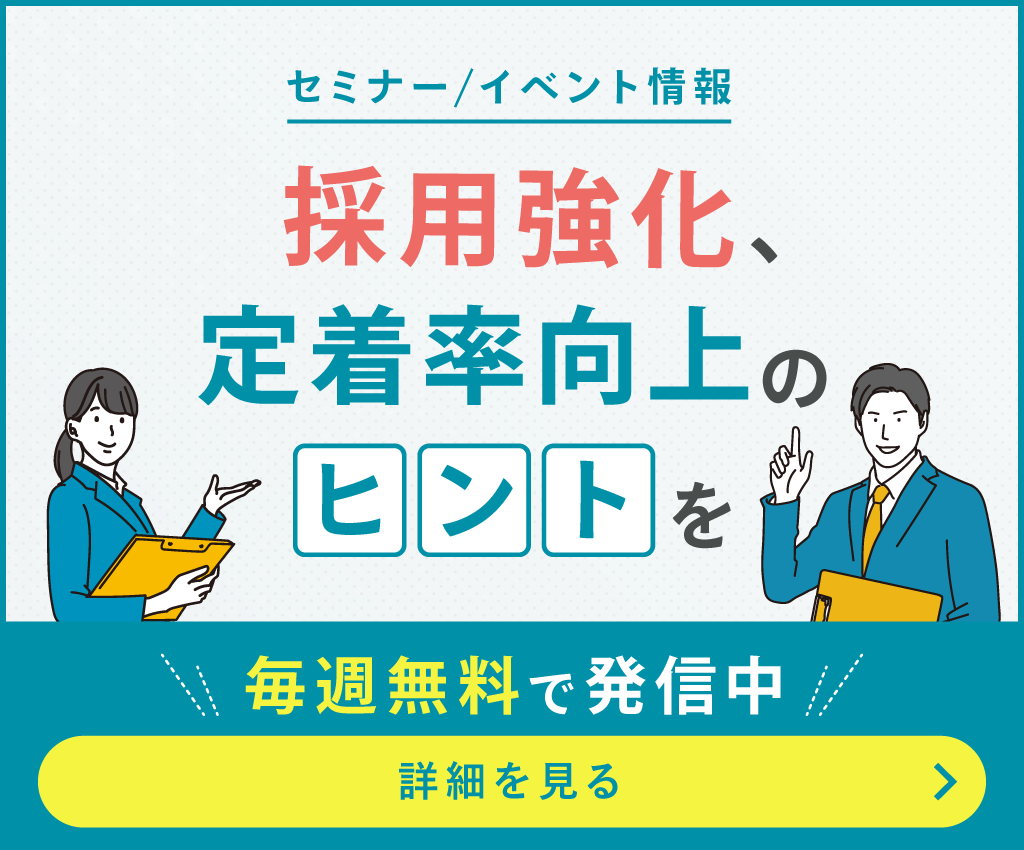
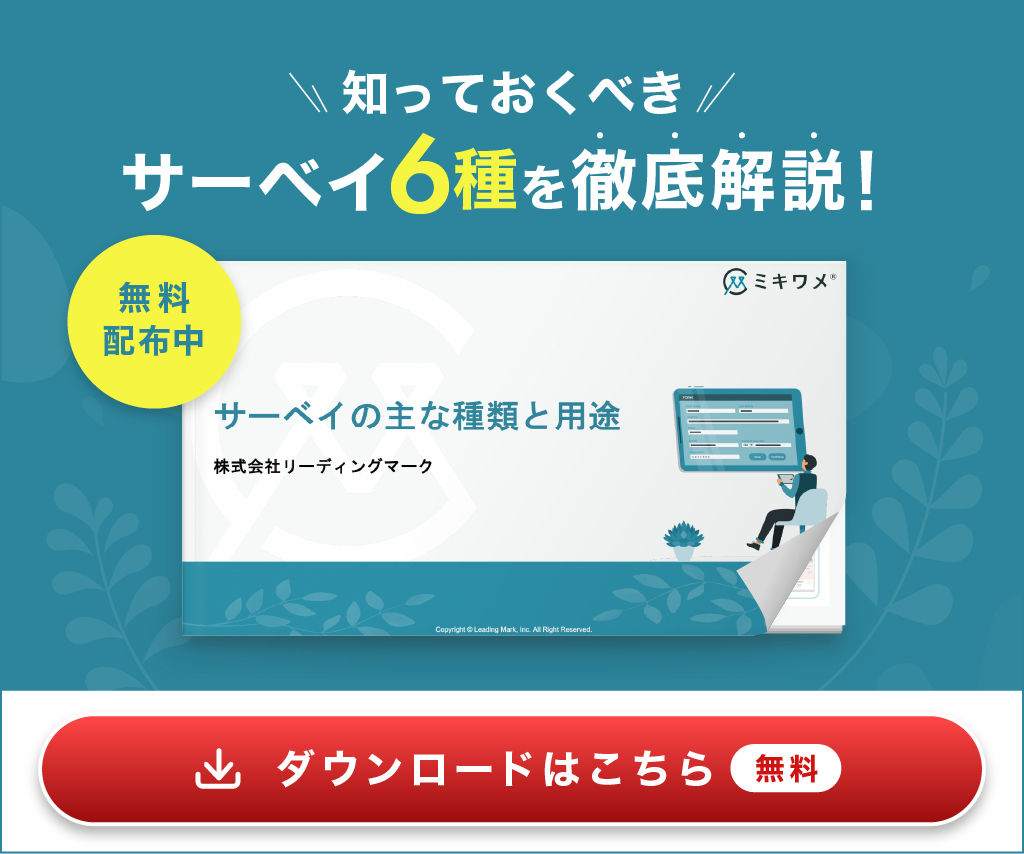
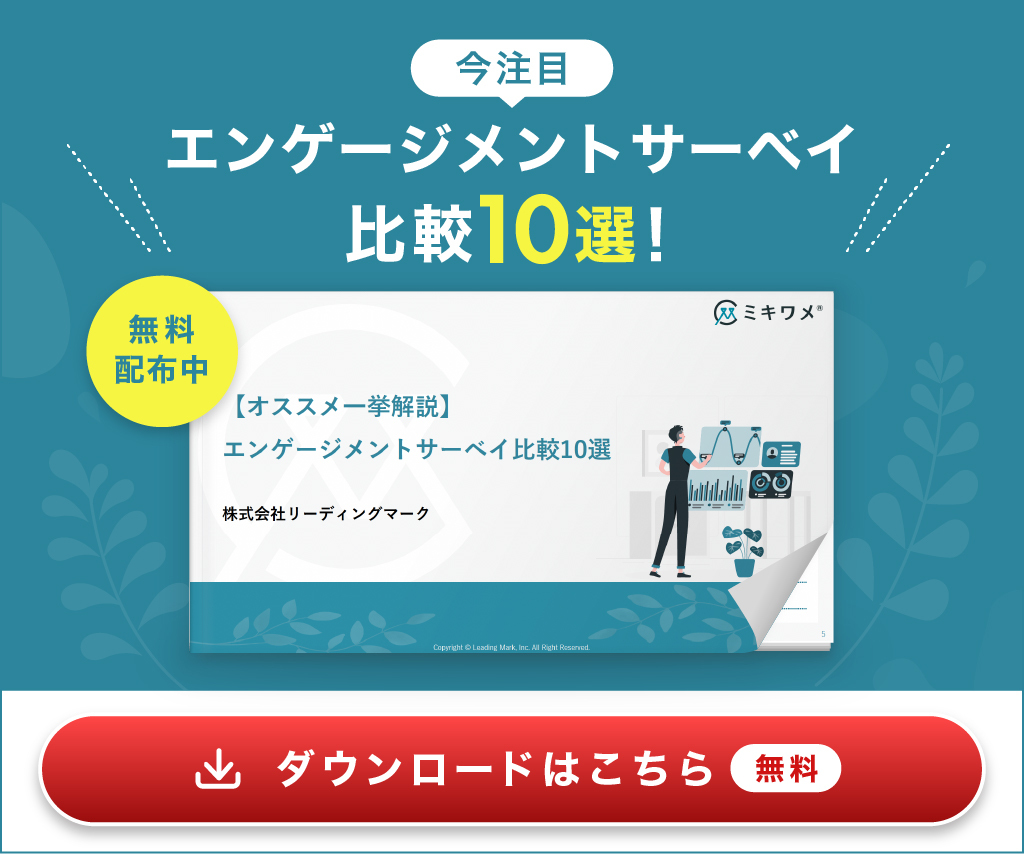
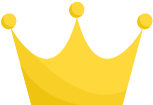 ランキング1位
ランキング1位 
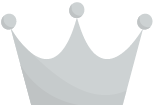 ランキング2位
ランキング2位 
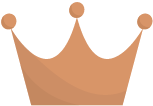 ランキング3位
ランキング3位